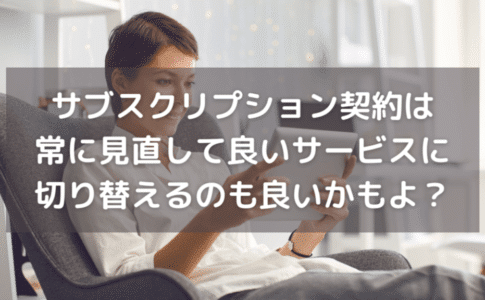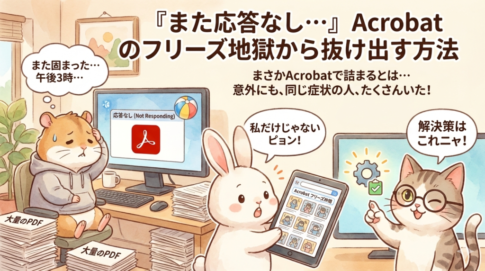先日、ふとしたきっかけで約10年ぶりにヤマダ電機へ行ってきました。
「え、10年も?」と自分でも驚くのですが、かつて私は家電量販店の中でパソコンサポート部隊として常駐していた身。だからこそ、退職後はどこか気恥ずかしく、まるで“昔の職場に顔を出すような気まずさ”があったんです。
それでも、千歳のテックランドがリニューアルしたと聞いて、「まあ、ちょっと見てみるか」と。ほんの気まぐれのつもりで立ち寄った10月19日の日曜日。そこに広がっていたのは、私の記憶とはまったく違う――まるでテーマパークのような空間でした。
おもちゃ売り場が3倍!? 家電よりワクワクしてしまう
驚いたのは、おもちゃ売り場の巨大化。
なんと3倍ですよ、3倍。かつて“洗濯機とプリンターの間”にひっそり並んでいたミニカーたちが、今では立派な王国を築いていました。
しかも、リフォームの展示コーナーや電動ソファー体験エリアまである。「これ…家電量販店だよね?」と思わずつぶやいてしまうほどの進化ぶり。いや、もう“ライフスタイル提案空間”ですよ。
中でも個人的に胸が高鳴ったのは――シルバニアファミリーが35%引き。思わず立ち止まって二度見しました。最近ちょっと趣味で集めているんですが、まさかここで出会うとは。あの可愛らしい動物たちが、いつもよりだいぶお手頃価格。ついでにスイッチ2の在庫もあって、「これはすごい」と唸りました。
アプリ時代の集客戦略に感心
オープニングセールの盛り上がりもさることながら、今のヤマダ電機は“アプリ戦略”が本気でした。新聞の折り込み広告が減った今、アプリを使った集客に完全シフトしているそうです。
私もルーレットに挑戦しました。「最低50ポイントか~、当たったら電池でも…」なんて淡い期待を込めた結果――200ポイント。まあ、人生そんなもんです。
でも、最大1万円分のポイントが当たるというから驚き。「昔の“紙のチラシ”より、こっちの方が夢あるじゃないか」と思わされました。
そして、気になる“パソコン売り場”へ
元・現場人間として、ここは見逃せません。
PCコーナーの前に立った瞬間、懐かしさと緊張が入り混じるあの感じ。
…けれども、デスクトップPCが一台もない。まさに郊外型店舗の象徴です。ノートPCがズラリと並び、その奥ではゲーミングPCブースにメーカー応援スタッフの姿。円卓型の受付カウンターにはお客様がぎっしり。ただ、接客しているのは携帯ショップのジャンパーを着たスタッフさんばかり。
「なるほど…そういう時代か」
パソコン販売もスマホ販売も同じテーブルで、“暮らしのデジタル化”を丸ごとサポートする形に変わっていたのです。
サポート料金を見て、思わず目が丸くなる
ただ、一番驚いたのは設定サポート料金の高さ。
「まるごと安心らくらくパック」――この響き、聞き覚えがあります。内容を見てみると、初期設定・アップデート・メール設定・ルーター設定などが全部込みで84,375円(一般価格)。
ただ、ここに少し引っかかる点があります。このパック、内容が重複している部分が非常に多いのです。たとえば、Windows Updateは初期設定中に自動で行われるものですし、メーカーアップデートやブラウザ設定も通常は無料の範囲。そして、最近はリカバリーディスクを作る必要もほとんどなく、USBメディアやクラウドで代替できます。つまり、昔ながらの「全部やります」メニューが、時代の進化に置いていかれている印象を受けました。
さらに驚いたのは、このパックにデータ移行が含まれていないこと。オプションで追加する場合、12,100円(50GBまで)から。容量が多ければさらに加算され、あっという間に10万円を超える計算になります。
そして、ウイルス対策ソフトの導入23,600円、メンテナンスソフト8,300円~13,090円、データ物理消去11,500円など、「パソコンを安全に使うための最低限のメニュー」を揃えると、初期費用だけで約12万円前後になるケースも珍しくありません。
もちろん、これらはすべて「お客様の手間を減らすためのサービス」なのは理解しています。昔、自分も同じようにサポートに入っていたので、裏側の大変さは身に染みてわかります。お客様の自宅に出向き、環境を整え、説明して、電話対応まで行う。一つひとつの作業にはコストと人件費がかかるんです。
でもやっぱり――冷静に考えると、“サポート費だけで新品ノートPCが買える”金額なんですよね。このあたりが、今の量販店における“価格の壁”なんだと思います。
月額サポートで「割引」しても実質同額
さらにもう一つ、見逃せないのが「ヤマダテクニカルサポートシルバープラン」という制度。これは月額3,480円(税抜)(年間45,936円)を払うと、設定サポートが半額になるだけではなくアフターケア費用が一部無料になるというもの。これに契約すると、84,375円のらくらくパックが約42,988円になるようです。
一見お得に見えますが年間サポート費(45,936円)+入会金(5,500円)で約51,436円。結果として合計で94,424円と、一般価格以上の価格になるんです。(しかも、この月額費用は毎月引き落とし…いわば“家電サブスク”のような形ですね。)
昔は“一度設定すれば終わり”という世界でしたが、今はクラウド同期やセキュリティ更新の頻度が上がり、メーカーも「継続契約」を重視している印象があります。まるで“サポートを買う時代”になったようです。
とはいえ、私のような独立系の修理店から見ると、この費用構造はやはり「高く感じる」のが正直なところ。うちでは同等の設定作業を実質無料(または作業費内で完結)で行っていますから、お客様からすれば「なんでこんなに違うの?」と感じてしまうのも当然です。
結果として、セキュリティソフトやデータ移行を追加すると形の無いものに12万円を超える結果となります。
もちろん、すべてお任せしたい方にはありがたい仕組みです。でも、私のように“中身を知っている人間”からすると、どうしても「ちょっと取りすぎでは…?」と感じてしまうんですよね。
パソコン本体も“量販店価格”の壁
さて、サポート料金に驚かされたあと、次に私がじっくり見て回ったのがパソコン本体の価格です。これは、正直なところ「さすが量販店」と言うべきか、「うーん…」と言うべきか――複雑な気持ちになりました。
展示されていたラインナップは、ほとんどがNEC・富士通・Dynabook・DELLといった大手メーカー。どれも安心感はあるのですが、スペックを見てみると、Core i5クラス・メモリ8GB・SSD 256GB~512GBという、ごく一般的な構成が中心でした。いわゆる「普通の家庭で使うなら十分」な内容ですね。
ただ、その価格が――だいたい13万円から17万円。昔なら“ハイスペックモデル”に手が届く金額です。それが今や、中間性能でこの価格帯。思わず心の中で「これ、同じスペックならBTOなら9万円台で買えるんだけどなぁ…」と、元サポートスタッフの血が騒いでしまいました。
さらに気づいたのが、展示モデルの多くに光学ドライブ(DVD)付きのものが多かった点。今どき外付けで十分なはずなのに、「いまだに“CDが入る安心感”を重視する層が多いのかな」と、ちょっと懐かしい気持ちになりました。でも、実際のところドライブ付きにするだけでコストも重量も上がるため、“軽量ノートを求める層”には少し不向きなんですよね。
今では定番になったコラボモデル
そして何より特徴的だったのは、型番の末尾に「Y」とつくヤマダ電機オリジナルモデルの多さ。これは見た目こそ既存メーカー品と同じですが、実は仕様が微妙に調整された専売品。つまり、同じ型番でもネット通販や他店では同等のスペック比較が難しくなっているのです。
この“オリジナルモデル”という言葉、聞こえはいいのですが、中身を見るとメモリがオンボード固定だったり、ストレージが片方だけだったりと、いざアップグレードしようと思うと拡張性が低いことも多いんです。もちろん、その分サポートを受けやすくするための工夫なんでしょう。ただ、PCの世界を知る者としては「ちょっともったいない仕様だな」と思ってしまいました。
実際、あるお客様から聞いた話では、「富士通製のノートパソコンを購入して初期設定込みで32万円くらいになった」とのこと。最初は冗談かと思いましたが、計算してみると確かに合点がいきました。本体17万円+設定8万円+セキュリティ・データ移行などの追加費用――あっという間に30万円台。パソコンが“高級家電”に戻りつつあるような印象さえ受けます。
とはいえ、これもすべて量販店の宿命です。人件費、店舗維持費、展示台数、サポート窓口の常駐コスト…。これらを考えれば、どうしても“利益を確保しなければ回らない”のが現実でしょう。それでも、やはり消費者の目線から見ると割高に感じてしまう。
だからこそ、私は「もっとパソコンを好きになってほしい」という思いで、自分の店ではできるだけ現実的な価格設定を心がけています。“高いからやめよう”ではなく、“これなら使ってみたい”と思ってもらえるように。
それでも、やっぱり楽しかった
とはいえ、白物・黒物家電、おもちゃコーナーの安さは本物。
Amazonと比べても安いものがいくつもありました。このあたりは、さすが家電量販店の底力。
そして何より――スタッフさんの接客が素晴らしかった。“安心会員に入ってください”ではなく、「よければGoogleの口コミで星5つお願いします」と笑顔でお願いしてきたのです。これにはちょっと感動しました。時代が変わっても、“人の温かさ”は変わらないんだなと。
10年ぶりの訪問で感じた「時代の流れ」
家電量販店は、もはや“モノを売る場所”ではなく“体験を提供する場所”に進化していました。アプリでの集客、口コミでの評価、SNSでの宣伝。10年前には想像もできなかった戦い方です。
私はもう量販店でパソコンを買うことはないかもしれません。でも――あの日のヤマダ電機は、「また来てみたい」と思わせるだけの魅力がありました。
店を出るとき、心の中でちょっとだけつぶやきました。「やっぱり、家電が好きだな」と。