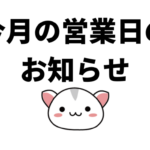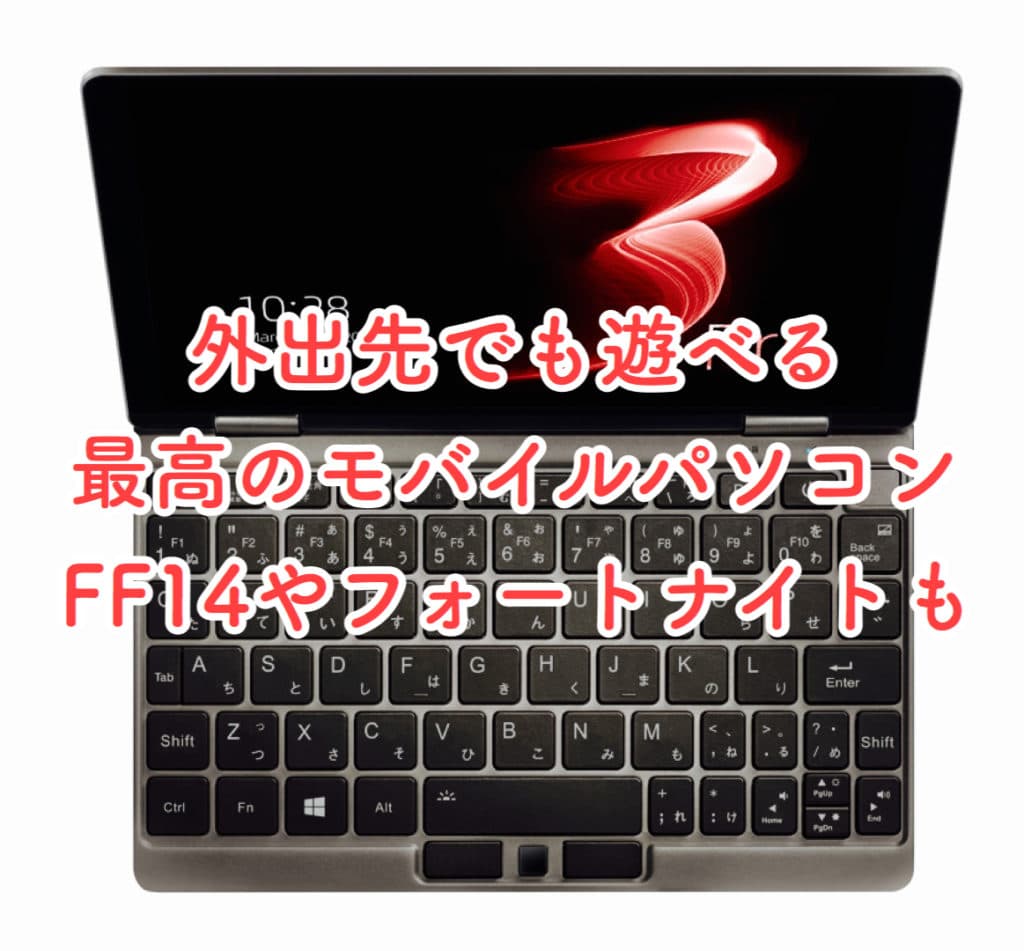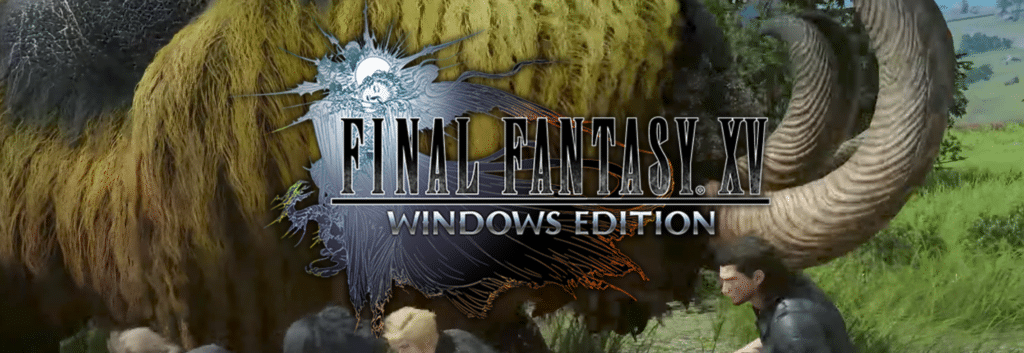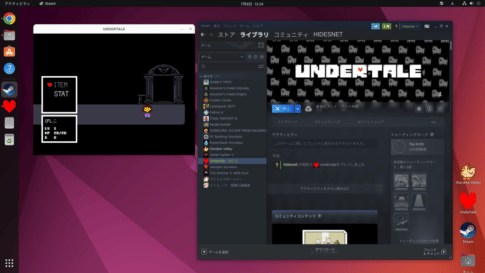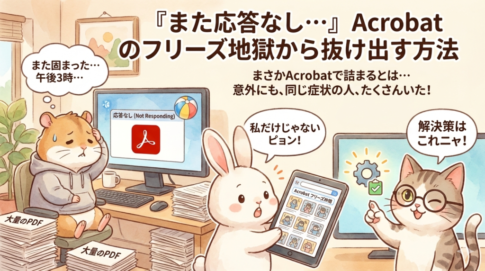ファミコンがまだ「幻の機械」だった時代
ドラゴンクエストI&IIが発売されました。
ニュースでその情報を見た瞬間、胸の奥がふっと熱くなる感覚がありました。「ドラクエか…」そう呟いたとき、頭の中には1985年のあの夏の匂いがよみがえっていました。
あの頃、私は8歳。ファミリーコンピューターという存在は、まるで遠くの町にいる“伝説のヒーロー”のようなものでした。うちにはまだファミコンがなく、ただ「ロードランナー」というカセットだけが、なぜか先に家にありました。
箱の中の黄色のカセットを、毎日のように眺めては想像の世界で遊んでいました。子どもながらに「これを動かせる日はいつ来るんだろう」と。いま思えば、あれは“希望”を手に入れた子どもの顔をしていたに違いありません。
ファミコン本体が届いたのは、それから半年ほど経ってからのこと。今で言えば、Switchがずっと入荷未定で買えず、ソフトだけ持ってる状態ですね。しかも私は、親戚が電気屋をやっていたので「そこで頼めば早く手に入る!」と思っていたのですが、結果的にそれが一番遅かったというオチ。今でもあのときの母の「まだ来ないの?」の声を思い出します。
初めてのドラクエ体験は「観戦」だった
さて、私が今回この話を書こうと思ったのは、「ドラクエが面白かったから」ではありません。正確に言えば、「ドラクエをプレイしていた人を見て、心が躍った」からです。
当時、親戚の兄がドラゴンクエストIを夢中でプレイしていました。私はといえば、横で座ってその姿を食い入るように見ているだけ。自分ではコントローラーを握る勇気もなく、ただ「レベルが上がった!」と聞くたびに一緒に拍手をしていました。
少年ジャンプの攻略記事を片手に、兄が深夜までスライムを倒している光景。あのテレビの光のちらつきや、洞窟の音楽が流れた瞬間の“ぞくっ”とする感じ。私の中では、全部が一枚の絵のように焼き付いています。
もしかすると、私はあの頃から「ゲームを遊ぶ」というより「物語を共有する」ことが好きだったのかもしれません。
初プレイはドラクエII ― そして初めての“全滅”
私が初めて実際にプレイしたのは『ドラゴンクエストII』でした。
これがもう、びっくりするくらい難しかった。
「敵が強い!」
「逃げられない!」
「書いたふっかつのじゅもんが読めない!」
…今ならSNSで嘆けますが、当時はそんな場所もなく、ただ一人で絶望していました。特に雪の国で全滅したときのあの“真っ白な画面”。あれは子どもながらに「世界の終わり」を見たような気持ちでした。
でも不思議なんですよね。それでも次の日、また電源を入れていました。やり直す気力が湧いてくる。「もう一度、あの町に戻りたい」そう思わせてくれるのが、ドラクエという作品の魔法だったのかもしれません。
RPGがくれた“想像力の種”
それから数年、ファミコンの世界はRPG全盛期へ。
『桃太郎伝説』『MOTHER』…
どれも心に残る作品ばかりでした。
特に『MOTHER』には衝撃を受けました。アメリカの田舎町を舞台にした少年の冒険。音楽、言葉、そして「やさしさ」が詰まっていた。
私はその原作本を小学生ながらに読み、ノートに好きなセリフを書き写していました。今思えば、あれが私にとって“物語を書く”という原点だったのかもしれません。
そして今 ― ドラクエI&IIで再び会えるかもしれない
40年の時を超えて、再び『ドラゴンクエストI&II』が発売されました。手に取った瞬間、私はあの親戚の兄の背中を思い出しました。レベルアップの音、呪文を覚えた瞬間の喜び、洞窟に入る時のあの静けさ。
今度は私がプレイヤーとして、あの頃の自分に再会する番です。まだ起動していません。でも、あのタイトル画面の音を聞いた瞬間、8歳の自分がきっと心の奥で「やっと会えたね」と笑う気がします。
世代ごとの“冒険の記憶”
人によって心に残る“冒険”は違うと思います。ポケモンに夢中だった世代もいれば、デジモンやモンハンで夜を明かした人もいる。けれど、私たち40代以上にとっての「原点」は間違いなくドラクエだった。
勇者の冒険を通して、私たちは「努力すれば強くなれる」「仲間がいれば乗り越えられる」ということを、小さなテレビ画面の中で教わった気がします。
そして今、私の手元には新しいドラクエがあり、当時のように少しワクワクしています。
時間に追われ、ゲームから離れてしまった大人たちへ。もし少しでもあの頃の自分を思い出したいなら、この『ドラゴンクエストI&II』を、年末の夜に静かに起動してみてください。
勇者はきっと、あなたの中にまだ眠っています。