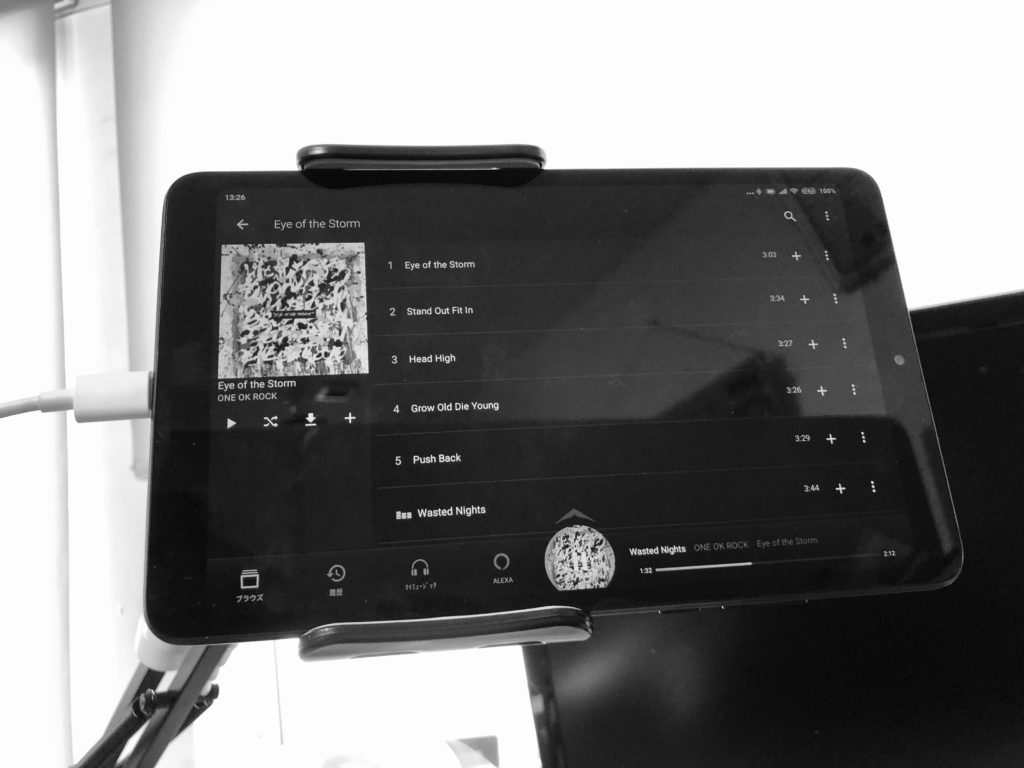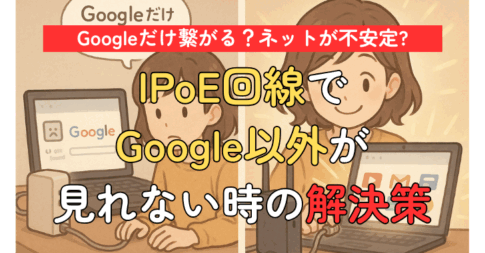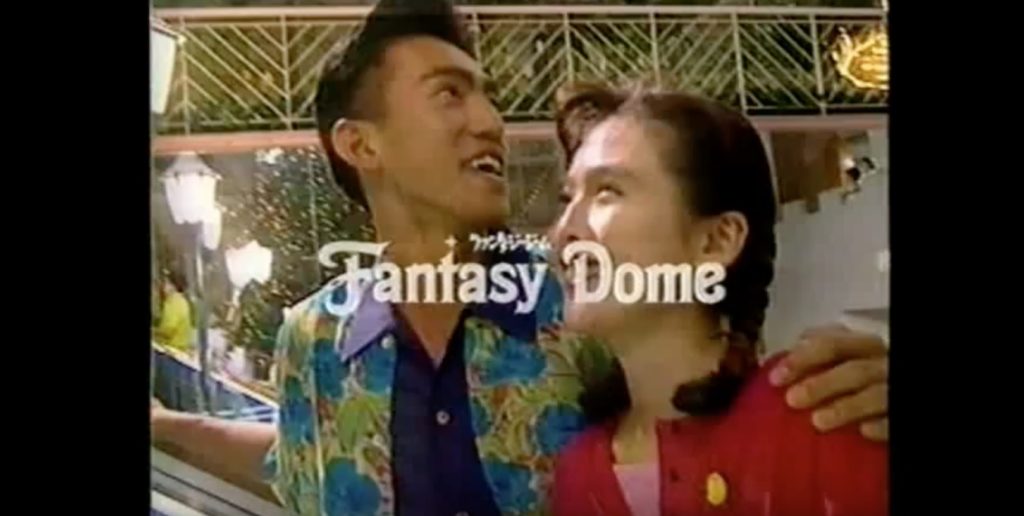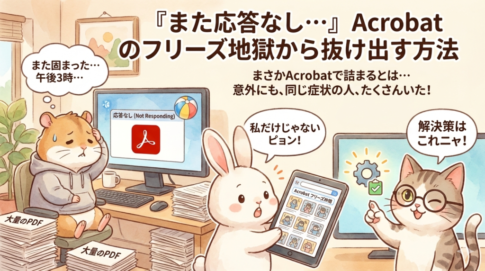最近、「GEO(生成エンジン最適化)」という言葉をよく耳にするようになりました。
SEOの次はGEOだなんて、まるで新しいゲームのステージのようですが、これは間違いなく“現実”の話です。ここ数ヶ月、私自身の現場でも「AI経由で来店されたお客様」がじわじわと増えているのを実感しています。
ChatGPTが“お店を紹介してくれた”という現実
ある日、お客様がこんなことをおっしゃいました。
「ChatGPTで“パソコンが動かなくなったときどうすればいい?”って聞いたら、近くにあなたのお店があるって出てきたんです」
……正直、背筋がゾクッとしました。Google検索で上位に出すために何年もかけて工夫してきたのに、気づけば“AIが代わりに紹介してくれる”時代になっていたのです。
思えば、昔は「パソコン 修理 苫小牧」で検索してもらうために、キーワードの位置や文章の構成まで気を配っていました。それが今では、「AIに信頼される情報」を書かなければ、誰にも届かない。――つまり、検索相手が“人”から“AI”に変わったのです。
GEOとは?AIに“信頼される存在”になること
GEO(Generative Engine Optimization)とは、生成AIが回答を作るときに「参考にする情報源」として自分のコンテンツを選んでもらうための最適化のこと。
今までは「検索結果の1位」を目指していたのが、これからは「AIの口から紹介されること」を目指す時代になりました。たとえば――
「パソコンが起動しない」とAIに質問したとき、「この問題については、パソコンサポート ピシコが推奨する方法をご覧ください」と紹介される。
これが、まさにGEOの世界です。SEOでは“クリックしてもらう”ことがゴールでしたが、GEOでは“AIの回答の中に登場する”ことがゴールになります。
「GEO?難しそう…」と思ったあなたへ:実は原点回帰の話です
GEOと聞くと、なんだか新しい技術っぽく聞こえますが、要するに「本当に信頼できる人が書いた情報」をAIが求めているというだけのこと。つまり、私たちが日々の現場で経験した“生の情報”こそが、最も評価される時代になったのです。
私自身、修理事例をブログに書くときに「この症状、実際にあった」「お客様の了承を得て記録した」など、できるだけ正確に書くようにしています。AIは、そうした「実体験に基づいた言葉」をちゃんと読み取ってくれるようになりました。逆に、どこかのサイトのコピペや一般論だけでは、もう評価されません。
つまり、「現場の声をそのまま書く」――それがGEOの第一歩なんです。
地域性を活かす:「苫小牧で信頼される修理屋」とAIに覚えてもらう
AIが提案する情報は、驚くほど“地域密着”です。
「この周辺でおすすめのパスタ屋は?」と聞くのと同じように、「苫小牧でパソコン修理できるところは?」と聞く人が増えています。そのとき、AIに選ばれるには「地域名+専門性」が欠かせません。たとえば、
- 「苫小牧市内でSSD交換が増えている理由」
- 「冬の北海道で多いパソコンの電源トラブルとは」
こうした、地域と季節、生活に結びついた情報がAIには強い。そして、それを地元の修理屋である私が書くことで、AIは「この人はこの地域の専門家だ」と判断してくれるようになるのです。
GEO時代に求められる“人間味”
AIは便利です。でも、AIがいくら優秀でも「お客様の不安を和らげる」ことはできません。パソコンが壊れたときの“焦り”や“恐怖”を受け止めて、笑顔で「大丈夫ですよ」と言えるのは、人間だけです。
だからこそ、AI時代にこそ「人間味のある情報」が大切になります。たとえば――
- 「自分で直そうとして余計に壊した」
- 「お客様の“あの表情”が忘れられない」
そんなエピソードも含めて書くことで、AIも人も“信頼”してくれるようになるんです。
正直、私もAIの勢いにはたまに怖さを感じます。でも、これだけは自信を持って言えます。AIは便利でも、“人に頼りたい”気持ちはなくならない。だからこそ、GEOはAIに勝つためではなく、「AIに紹介してもらう」ための技術なんです。
AIと競うのではなく、“共に働く”時代へ
GEOの本質は「AIの時代に、どうやって人の想いを届けるか」ということだと思います。私たちパソコン修理業は、単に機械を直すだけでなく、“人の不安を直す仕事”でもあります。
これからは、AIに自分の存在を知ってもらい、困っている人のもとに導いてもらう。そんな、「AIと共存する修理屋」を目指していければいいなと思います。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、AIにとって信頼されるということは、つまり“世の中から本当に必要とされている”という証拠でもあるのです。
最近、キングコングの西野亮廣さんのブログを読んでいて、とても印象に残った言葉がありました。それは「後継者がいないと嘆いている人が居たなら、そこで跡継ぎをしてください」というものです。
理由はシンプルで、それはAIでは受け継げない“人の仕事”だから。たとえば農業の現場でもそうですが、畑の感覚や土地の癖、地域との関わりといった「経験の積み重ね」は、どんなAIでも真似できません。私たちのような修理業も同じです。機械を直すだけならAIができるかもしれませんが、「お客様の想いごと受け取って直す」ということは、AIには絶対にできない。
私はそれを読んで、まさにその通りだと思いました。パソコン修理の技術も、接客の空気も、経験から生まれる勘も――どれも“人”だからこそできること。
AIはそれを奪う存在ではなく、むしろ私たちの努力や情熱をより多くの人に届けてくれる存在なのかもしれません。だからこそ、臆することなく、上手にAIを使いこなしていく。それが、これからの時代を生き抜く“人間らしい生き方”なのだと思います。
そして、その第一歩は――「今日も、ひとりのお客様のパソコンを丁寧に直す」そこから始まります。