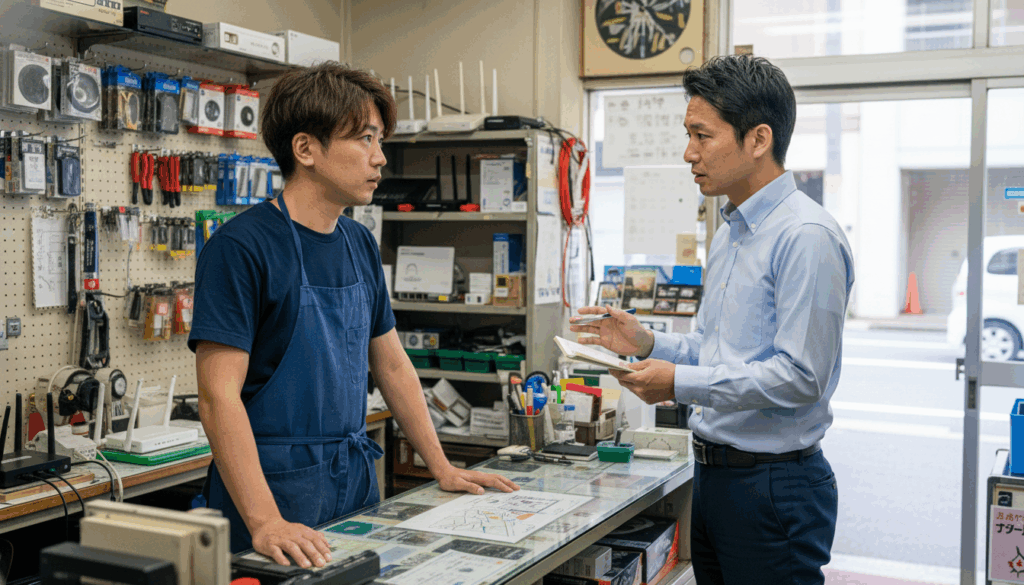
ここ最近、事業主さんからのご相談でじわじわ増えているのが、
という内容です。実際に話を聞いてみると、皆さん口をそろえておっしゃるのが、
つまり、「ネットがないと生活が成り立たない」という感覚なんですね。
理由はシンプルで、海外の方は日本人ほど「電話回線での通話」を使っていません。代わりに使っているのが WhatsApp というアプリ。日本でいうところの「LINE」です。
- 家族とのビデオ通話
- 母国のニュースや情報収集
- YouTubeやSNSの閲覧
これらがすべて、WhatsApp+Wi-Fi のセットで完結してしまう。だから、住む部屋の条件として「Wi-Fiがあるかどうか」はほぼ必須になっているわけです。
私たち日本人が「お風呂がない部屋はちょっと…」と思うのと同じくらい、外国人労働者にとっては「Wi-Fiがない部屋はちょっと…」なのだと感じています。
アパート1棟まるごとWi-Fi、相談内容はどんどん大きくなっている
昔は、
- 一軒家に複数人で住むパターン
- アパートの1室だけを寮として使うパターン
が多かったので、Wi-Fiルーターを1台置いて終わり、でどうにかなっていました。ところが最近は、
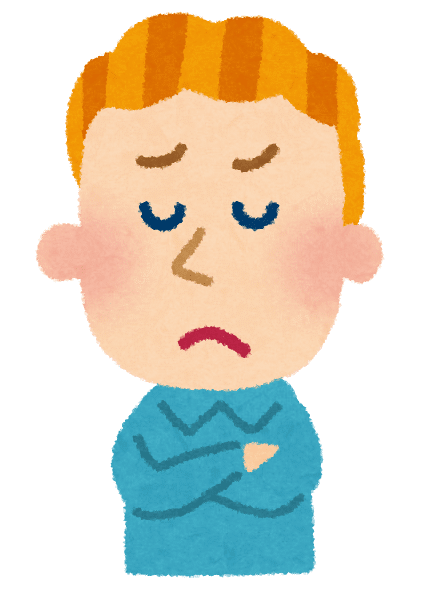
「アパート1棟まるごと借り上げ(もしくは購入)して、そこを全員分の寮にしているので、全戸でネットが使えるようにしたい」
というご相談が増えています。ここまでくると、さすがに
だけではまったく追いつきません。部屋数が多くなると、
そして最終的に、その矛先はオーナーさん(雇用主)に向かうことになります。
まず整理したい「2つの視点」
ここからが本題です。アパート1棟にネット環境を入れるとき、いきなり
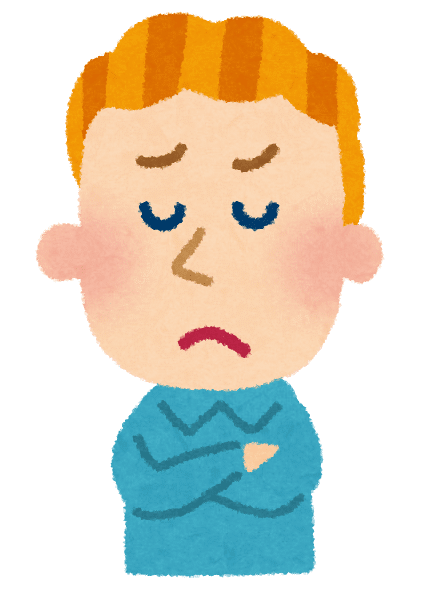
「業者さんに任せるか、DIYするか」
で悩み始める方が多いのですが、その前にぜひ整理してほしいポイントが2つあります。
1つ目:建物の「物理的な条件」
- 各部屋までLANケーブルを通すための配管(CD管)があるか
- そもそも昔ながらの電話線しか来ていないのか
- 壁の中に新しくケーブルを通せる余地があるのか
こういった「建物の構造」が、工事費用や方式をほぼ決めてしまいます。
- 新しめの物件 → もともとLAN配管が用意されていることが多い
- 古い物件 → 電話線の配管しかなかったり、そもそも配管が厳しかったり
前者なら、LANケーブルで各部屋まできちんと配線できる可能性が高いですし、後者だと、既存の電話線を使う方式や、露出配線(壁の外側にモールで這わせる)に頼ることになります。
この時点で、DIYが現実的かどうかも見えてきます。
2つ目:誰が「ITヘルプデスク」になるのか
もう一つ大事なのが、運用の視点です。
- 「Wi-Fiが繋がらないんですが」
- 「パスワードを忘れました」
- 「動画がカクカクして見れません」
こういった問い合わせに、誰が、何語で、何時まで対応するのか。DIYで全部自前でやるということは、
オーナーさん自身が「24時間なんちゃってITサポートセンター」になる
という覚悟が必要です。
これは大げさではなくて、本当に夜の22時とかに
「今日どうしても家族とビデオ通話したいのに、繋がらない」
と連絡が来ることがあります。そのときに、設定を一緒に見てあげられる人が社内にいるのかどうか。ここを見落として「初期費用が安いからDIYで!」と決めてしまうと、精神的にも時間的にも、後から大きくしわ寄せが来るパターンを何件も見てきました。
代表的な4つの導入パターンをざっくり整理
現場でよく目にするパターンを、あえて乱暴に4つに分けてみます。
モデルA:フルDIY(自作)モデル
工具が使える人なら、技術的には不可能ではありません。配線作業は電気工事士の資格も不要な範囲のことが多いです。
ただし問題はここから。
「とりあえず安くあげたけど、入居者満足度は低い」という結果になりがちで、小規模(2〜3世帯)以外にはあまりおすすめできないのが正直なところです。
そしてもう一つ、地味に怖いのが「プロバイダとの契約条件」。個人向けの安いプランで「第三者への再提供」が禁止されているケースが多く、それを知らずにやると、最悪「契約解除→アパート全戸ネットなし」という事態もありえます。
モデルB:業者に頼むが、共用部に強いWi-Fiを置くだけ
工事は比較的シンプルで、初期費用も抑えやすいです。ただし現実には、
という「あるある」が頻発します。
安く済む代わりに、通信品質は妥協が必要というモデルです。「とりあえずネットが全く使えないわけではないけど、快適とは言い難い」レベルを受け入れられるかどうか、という感じですね。
モデルC:業者に頼んで、各戸にちゃんと配線(おすすめ)
手間も工事費もいちばんかかりますが、「安定性」と「入居者満足度」でいえばこれが一番強いです。
正直、外国人労働者向けに「ちゃんとした寮」を用意したい事業主さんには、このモデルを第一候補として考えていただくのがいいかな、と私は思っています。
もちろん、初期費用はそれなりにかかります。ただ、アパート経営や人材確保の観点で見ると、
半年空室が続いたら、それだけで何十万円も売上が飛ぶ
という現実もあります。
「無料Wi-Fi付き」を強みとして出せるなら、空室対策+福利厚生への投資と考えた方が、長い目ではむしろ安くつくことが多いです。
モデルD:一部の部屋だけ導入する「スモールスタート」
一棟まるごとの工事費をすぐに出すのが難しい場合や、「本当に入居が増えるのか様子を見たい」という時に向いたやり方です。
最初から全力投資するのではなく、
- まずは一部分で効果を確認
- 入居状況や満足度を見てから、全戸導入を検討
という段階的な進め方も、リスクを抑える意味ではかなり現実的です。
法律まわりは「電気通信事業法」よりも「契約条件」に注意
ここで少しだけ、堅い話も触れておきます。
結論だけ言うと、
- アパートオーナーが「設備として無料Wi-Fi」を提供する
- 利用料を別途取らず、家賃や共益費に含めている
という形であれば、電気通信事業法の「事業者」には該当しないとされています。つまり、「総務省に届出が必要な立派な電気通信事業」にはならないケースがほとんどです。
それよりむしろ怖いのが、さきほど少し触れた
「個人向け光回線を、第三者に再提供してはいけません」
というプロバイダ側の利用規約です。DIYで安く済ませようとして、家電量販店の個人プランを契約し、それをアパート全戸に分配してしまうと、契約違反になる可能性が高いです。
なので、
このどちらかが、安全な選択肢になります。
導入までの「ざっくり流れ」をイメージしてみる
専門業者に任せるパターン(おすすめ側)
- 業者候補をいくつかピックアップ
- アパート一括導入専門の業者
- 地元のケーブルテレビ会社
- 大手プロバイダのアパート向けプランなどから、最低でも2〜3社。
- 現地調査と見積もり
実際に建物を見てもらい、構造や配管の状況を確認してもらいます。そこで「各戸配線にできるか」「電話線を使う方式になるか」がほぼ決まります。 - プランとサポート内容を比較
- 初期費用
- 月額費用
だけでなく、 - 入居者からの問い合わせを直接受けてくれるか
- サポート窓口の時間帯
なども重要です。
- 契約・工事日程の調整
- 工事・開通 → 入居者への案内配布
SSID・パスワードを書いた紙と、「トラブル時はここに電話してください」という連絡先をセットで配ります。
この形であれば、オーナーさんは細かい技術対応からかなり解放されます。
DIYでやる場合のざっくり流れ
- 法人向け光回線の契約(ここ重要)
- 建物の簡単な配線設計
- LANケーブル・工具を揃える
- 共用部から各部屋へ配線、部屋ごとにWi-Fi機器設置
- ネットワーク設定(IP・SSIDなど)
- その後の問い合わせ対応を、すべて自前でやる
正直、「PCやネットワークが本業です」という人以外には、かなりハードめです。さらに、問い合わせ対応が本業の時間を圧迫し始めると、「安くしたつもりが高くついた」パターンに入りがちです。
結局「いちばん安くつく」のはどれか
ここまでをまとめると、こうなります。
外国人労働者の方々にとって、
- 安定したWi-Fiがあるかどうか
- 家族とストレスなくビデオ通話できるかどうか
は、働き続けるうえでの満足度に直結します。
オーナー側から見ても、
- 「無料Wi-Fi付き」「スマホ1台あればすぐ使える」
というのは、求人や入居募集のときに出せる立派な強みです。
おわりに:Wi-Fi設備は「福利厚生」と「空室対策」の中間みたいな存在
私自身、PCサポートという立場でこうした相談を受けていると、
「どこまで自分たちでやるべきで、どこからを専門家に任せるべきか」
という線引きに悩んでいる事業主さんが多いなと感じます。Wi-Fi環境の構築は、その典型例です。
外国人労働者の方々の生活を支えるインフラだと思えば、ここは「安さだけ」で決めるより、
- 建物の条件
- 将来の運用負荷
- 入居者の満足度
このあたりをセットで考えていただくのが良いのかなと、現場でお話を伺いながら感じています。
もし、
「うちの物件だと、どのパターンが現実的なんだろう?」
「とりあえずメッシュWi-Fiで小さく始めるとしたら、何を注意したらいい?」
といった個別のご相談があれば、その物件の間取りや部屋数を教えていただければ、もう少し踏み込んだ形でお話もできるかなと思います。




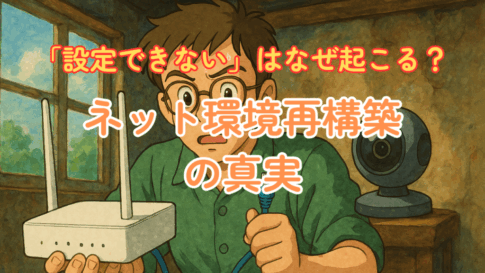




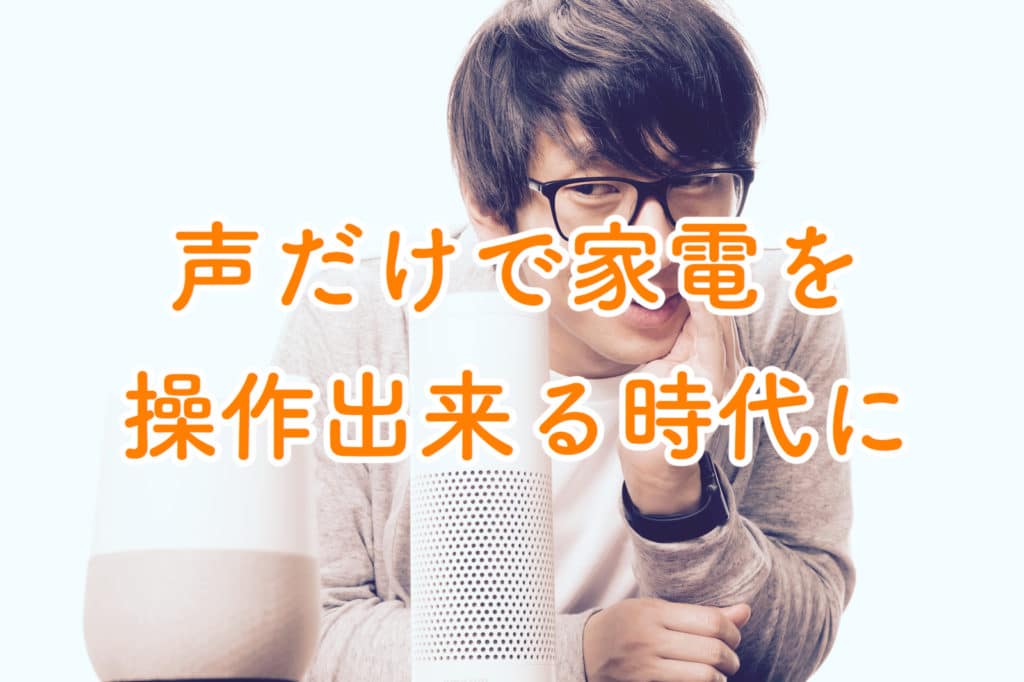



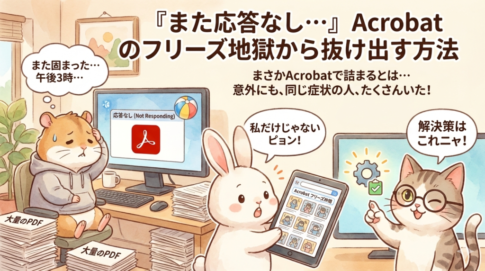


「うちで雇っている外国人スタッフの寮(アパート1棟)に、Wi-Fiを入れたいんですが……何をどうすればいいですか?」